感情の入口:安心と不安のあいだでざわつく胸の内
国土交通省の「大規模土地取得で取得者の国籍を自治体に届け出、2026年度に国で一元化する」という発表を聞いて、まず湧いたのは二つの感情だ。ひとつは「やっと実態に手をつけるのか」という安堵。水源や森林保全という公共目的は正当で、未然に不適切利用を抑える狙いは理解できる。だがもうひとつは、数字が示す現実を目にしてしまったことから来るざわつきだ。実際、昨年だけで外国人や外国法人に買われた農地は合計175.3ヘクタール、東京ドーム約37個分にも相当するという報告がある。しかも中国籍が最多など、国籍別の偏りも見える。こうした現状を前に、国籍情報の収集がどこまで妥当な「手段」なのか、肌感覚として不安が混じるのは自然だろう。

内省:目的と手段は整合しているか — 国籍が最良のトリガーなのか
自分のざわつきの正体を掘ると、核心は単純だ。政策設計が「目的に対して最も適切な手段」を選んでいるかどうか、そこに懸念がある。農林水産省の調べでは、外国人個人や外国法人による農地取得が実際に増えており、国籍別では中国、韓国、ブラジル、米国などが並ぶという事実がある一方で、農地法の下では「営農目的」での取得が前提とされ、投資目的の取得は制限されるはずだ。では、国籍を届け出させることが、投機的取得や水源・森林の不適切利用を最も効率よく防げるのか。代替案として、事業計画の透明化、登記や納税履歴、資金の出所の提出といった「利用実態に近い」指標を優先する設計は考えられないだろうか。国籍というラベルは確かにリスクの一側面を示すが、それだけに依存すると「外国人=危険」という短絡を助長しかねない。政策は安心を作るためのはずだが、やり方次第で不安を種に変えてしまう。
社会照応と問い:透明性・比例性・説明責任をどう担保するか
制度が動き始めれば、自治体と国の事務負担は増える。データベースが整備されれば、その利用範囲とアクセス権限が問題になる。農地の取得事例は地域ごとにばらつきがあり、昨年は日本在住の外国人377人が合計95ヘクタールを取得、外国法人による取得も確認されている。だからこそ、施策には三つの原則が不可欠に思える。第一に目的限定――収集したデータは森林・水源保全や土地利用監視という明確な公共目的以外に使用しない法的担保。第二に最小限情報の原則――国籍を最初に掴むのではなく、利用目的や事業性、転用リスクといった直接的な情報を優先的に収集・審査すること。第三に独立監視と説明可能性――第三者機関による定期監査と、自治体・国が運用状況を公開する仕組みだ。これらが欠ければ、短期的に安心を産んでも中長期的には地域の投資環境を冷やし、住民間の不信を拡大する恐れがある。
最後に問いを投げる。私たちは何を守るために国籍情報を求めるのか。それは本当に国籍でなければ代替できないのか。そして、その情報管理を誰に、どのように委ねるのか。 数字(東京ドーム換算や国籍別内訳)が示す現実を無視して議論を進めることはできない。だが同時に、数字を根拠に「属性」へ短絡的に向かうのも危険だ。政策の正当性は、細部の設計力と説明責任によって担保される。私たちが求めるのは、恐れに任せた単純な閉鎖でもなく、無条件の開放でもない——慎重で説明可能なガバナンスであるべきだ。


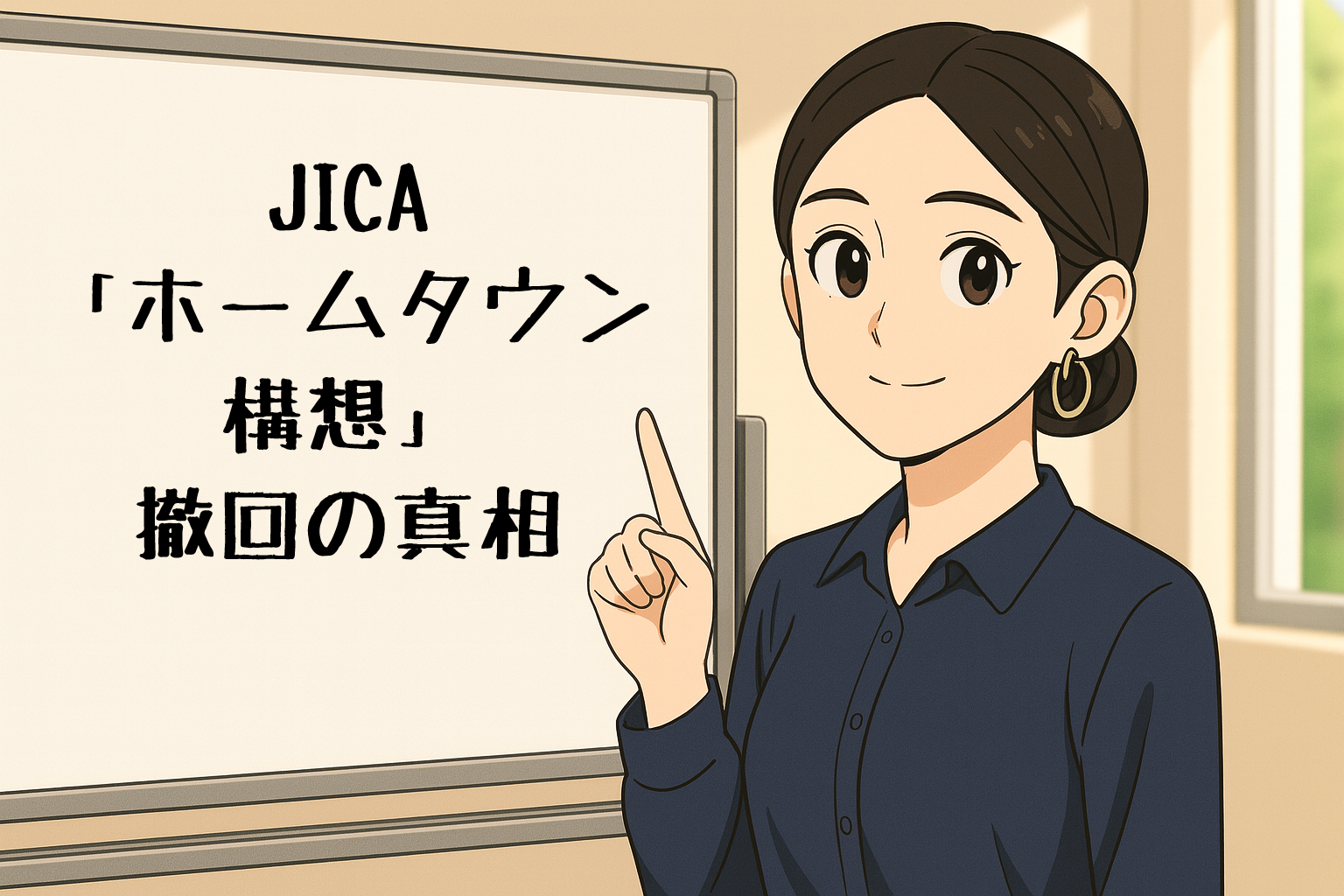
コメント